あ行の作家
長い廊下がある家有栖川有栖・光文社
11/01/04
 火村シリーズの短編集。
火村シリーズの短編集。【長い廊下がある家】
道に迷った青年がたどり着いたのは、幽霊が出ると評判で雑誌のクルーが取材に来ていた廃屋だった。その地下道で死体が見つかる。けれどそこは密室のはずで──。
空間認知力が激しく劣っているので、脳内でいろんな図面がぐるんぐるんしている。いまだにちゃんと分かったかどうか自信がない。が、面倒なはずの設定でもくいくい読ませてしまうのがリーダビリティの高さだよなあ。
【雪と金婚式】
雪の日に起きた殺人事件。ある事に気付いた関係者が、それを警察に届ける直前に事故で記憶を失ってしまう。彼はいったい何に気付いたのか──?
まずこの設定が魅力的! 事件そのものじゃなくて、何に気付いたかを探るっていうのがいいなあ。そしてこの解決のロマンティックなことと言ったら。
【天空の眼】
心霊写真に怯える女子学生。しかしその背後にあったものは──。
トリックそのものより、なぜ心霊写真だなどという話になったのか、そちらの方に膝を打った。あ、トリックがダメってんじゃないのよ。あたしは物理的なトリックには惹かれないクチなのでそちらの印象が残りにくいというだけの話です。でもそういう読者であっても、トリックの萌えなさ加減を補ってあまりある動機、そして動機に気付く過程、そういうあたりでちゃんと楽しめる。
【ロジカル・デスゲーム】
火村だけの物語。過去に起きた事件について、父が話したいと言っている──そんな申し出を受けてとある人物の家に向かった火村だったが、そこで彼はある賭けをつきつけられる。死ぬか生きるか、確率の問題。火村が〈ロジカルに〉考えて出した答とは?
本作品集の中でイチオシ。これの何に感心したって、確率の問題として解くことは可能なのよ。中でも解説されてるけど、この賭けはそのスジではけっこう有名な話(何年か前になまもの日記でも取り上げたよね)で、自分が助かる確率を大きく上げる方法がある。けれど。その方法を知っているからと言って、事件が解決されるわけではないってことに注意したい。賭けに勝つことが目的ではなく、事件を解決することが目的なんだから。
でもそれは、ともすれば本格ミステリではないがしろにされがちな部分でもあるんだよね。論理的にWHOやHOWを突き詰めるのが本格ミステリなので、「論理はさておき皆でハッピーになろうぜ」みたいなケースは無視されちゃうことが、ままあるのだ。もちろんそれはそれで理解できる趣向だけど、まあ、なんつーの? オトナの解決っつーの? そういうのが要求される場って、断固として存在するじゃん、ねえ?
本編はそのひとつの形。「オトナの解決」を「ロジカルに」導き出している。もちろんこれも論理ゲームの一種ではあるけれど、勝負に勝つための論理ではなく、解決させる手段としての論理であるところに強く感じ入った次第。
メグル乾ルカ/東京創元社
10/09/23

おお、ステキな連作短編だ。ファンタスティックで、でもリアルで、ちょっぴり怖くて、そして最後は暖かくて。
物語の始まりはどれも、大学の学生部。ユウキという女性職員が、バイトを探しに来た学生に「あなたはこれよ。断らないでね」と勝手にバイト先を指定する。仕方なくバイト先に赴いた学生たちを、不思議な奇跡が待っている──というお話。
通夜の夜に遺体のそばで一晩過ごす「ヒカレル」、病院の売店での商品整理をする「モドル」、飼い主の旅行中に飼い犬に餌をやる「アタエル」、雇い主が作った豪勢な料理をただ食べるだけの「タベル」、そして庭木の冬装備をはずす「メグル」。
「ヒカレル」はホラーテイスト、「モドル」はミステリ、「アタエル」はサイコサスペンス、「タベル」はファンタジー、「メグル」は幽霊譚、というふうに分けようと思えば分けられる。けど細かくジャンル分けせずとも、ざっくりと「不思議で怖くて暖かい話」と表現するのが一番いいかも。
ただ特記しておかねばならないのは、いずれも奇跡の物語であるにも関わらず、登場人物や物語の設定は実に地に足の着いたリアルなものであるということ。「ヒカレル」で描かれる、ひとりで死ぬ事の寂しさ。「モドル」「タベル」に登場する病気の現実。「アタエル」で明らかになる家族の問題。「メグル」で描かれる理不尽な運命。
詳細を書くとネタバレになるので書かないが、誰もが向き合う可能性のある〈不幸〉に、ときには当事者として、そしてときにはちょっと関わるだけの間柄として実際に向き合ったとき、どんな葛藤を抱き、それをどう解決して行くかというところに本書の眼目はある。ファンタジックな演出は、それを後押しするに過ぎない。根っこがリアルで、ディテールが具体的だからこそ、ファンタジックな展開も生きる。特にお薦めは「モドル」。これは確か推理作家協会だか本格ミステリ作家クラブだかの年鑑にも捕られてたんじゃなかったかな。最もファンタジィ風味の少ない一編。
個人的にのけぞったこと。5つの短編のうち3つに病気のエピソードが出てくるのだが、そのうち2つが、あたしのごく身近にいる人と同じ病気だったのだ。ひとつはメジャーな病気だけど、もうひとつはマニアックというかマイナーというか、けど難病指定されてる知る人ぞ知るって病気で。まさか自分に近いところにある病気が続けざまに連作短編集に出て来るとは。読む側として感情移入も一入。
それが奇跡で治るものよりは、治らないという現実にちゃんと向き合うものの方が、個人的には読んでて納得できたな。ま、それは個人的な事情だけど。
魔法使いの弟子たち井上夢人/講談社
10/09/22

あたしが最も読んでて辛い話、それは「自分ではどうしようもないこと、自分には何の責任もないことで、理不尽に周囲から排斥され、虐げられる」という話だ。小公女とかさ。アンネの日記とかさ。橋のない川とかさ。こういうのって本人の自助努力だけでは解決できず、周囲や環境や状況が何か変わるのを待つしかない。だから読んでて辛い辛い辛い。そして本書にも、そういう要素がある。
本書では、凶悪な伝染病から奇跡の生還を果たすも、後遺症として超能力を得てしまった3人が登場する。千里眼になった京介。念動力を得ためぐみ。本当は九十代なのに三十代の体に若返った興津。
まずめぐみは、致死のウィルスを運んだ張本人として近所の人から人殺し呼ばわりされる。実家も焼かれている。これはね、嫌な話ではあるけど、分かるのよ。いくら本人にその自覚がなかったとはいえ、そのせいで病気を移され家族を亡くした人にしてみれば、どれだけ悔しく、腹立たしいか。だからめぐみ本人も、人殺しである自分というものを可哀想なほどに自覚してる。
でも、問題はこの先。超能力を得た彼らは、最初は面白がられる。けれどある事件がきっかけで、世間は彼らを危険なものと認識し、恐れ、──そして狩ろうとするわけだ。
でも、小公女やアンネの日記とは大きく違うところがある。それは、彼らの超能力が半端なくすごいこと。従来の超能力の概念を超えちゃうくらいの、万能っつかスーパーマンつか、早い話が彼らは誰が攻撃してきても圧倒的に強いのよ。彼らが本気で戦おうとするなら、絶対負けないのよ。これは超能力なんてもんじゃない。魔法。だからタイトルが魔法使いの弟子たち。
自分たちには特殊な能力があって、それは別に望んで得たものではなくて。だから自分なりにその力に折り合いをつけ、生きていく方法を探る。特にめぐみの決意や努力は涙ぐましいほど。だけどその能力故に人を巻き込み不幸にしてしまうという事実があって。ここの葛藤が読みどころ。
そんな状況で、どうすれば平和裏にすべてを解決することができるのか。読者は彼らの視点に立ってるから状況がわかるし感情移入もできるけど、世間はそうはいかない。本書では警察ってのがすごく頭の固くて面子にこだわる勢力として描かれてるけど、同じ設定で今野敏あたりが警察視点で書くと、きっと警察の行動に理があるように思えて来るだろう。それくらい信じられない能力を彼らは持ってるわけだから。それは即ち、自分がこの場にいたらやはり彼らを恐れ、異端視するのではないかという、自分に対する不信すら生む。
超能力のすごさ、それを発揮するシーンの盛り上がり、科学ミステリとも言える仕掛け、アクションシーンの臨場感など、もうページをめくる手がとまらない。そんなエンタメ満載のベースに、人から異端視されるという悲しみが漂う。そこがいい。
このラストは賛否両論あるかもしれないが、あたしはアリだと思う。てか、このラストで救われた気持ちになった。と同時に、もう一度恐怖が甦ってきた。救いと怖さと余韻のある、巧い終わり方だと思う。
あ、救いと言えば、(もちろんいろんな思惑があるとは言え)彼らに近い場所にいた病院関係者だとか、職場の人たちだとかが、彼らが人類を超えた能力を持ったと分かってからも彼らを理解し、助けようとしてくれたことも挙げておかねば。そういう理解者の存在は、「理不尽に辛い話なんか嫌だよ」というあたしのような読者にとっても助けになった。
キケン有川浩/新潮社
10/09/19

ああ、やられた。これにはやられた。
キケンとは、成南電気工科大学のサークル、機械制御研究部のこと。即ち、機研。新入生の元山と池谷が二回生の上野から勧誘され、入部を決めたは良かったが、このサークルの上級生はまさに「キケン」だった。もちろんこちらは「危険」の方。
そこから1年に渡るキケンでの熱い熱い青春が回顧形式で語られる。春は新歓、初夏は恋、秋は学祭、そして冬の終わりにはロボット相撲。ひとつひとつはホントにこの著者らしく、善くも悪くもマンガなのよ。理系大学の実作サークルの、ある一面をデフォルメして面白く仕立てて。登場人物にも個々それぞれに一定の方向付けがなされているという、つまるところ「多面的で不確定な人間」ではなく、あくまでも「役割を持ったキャラクター」。それをわざと──というか、最初からそういうものを書きたくて、確信を持って書いている、という作風。テンポ重視で、軽くて、ボケとツッコミがあって、キャラが立ってて、アクションもあって、トラブルに出会っても必ず最後は解決するのがわかってる安心感もあってという、ホントに爽やかなマンガの王道なのね。
一昔前までは「マンガみたい」というとそれは悪口だったのだが、今やそんなふうに解釈する人もいないだろう。むしろ上に書いたようなマンガならではの魅力や個性といったものをテキストだけで十全に再現するというのは至難のワザだ。本物のマンガである挿画も一端を担っているとは言え、本書はまさに「読むマンガ」を体現している。映像、音、迫力、疾走感──それらを文字だけで作り上げ読者の五感に響かせている。相当の筆力と構成力がなければできないこと。
ただ……シンプルでベタなストーリー展開は、楽しいけれどそれだけだよな、と思いながら読んでいた。面白いし笑っちゃうし読み出したら止まらないテンポもあるけど、でも、話としてはよくある種類のもんだよな、と。ところが。そんな斜に構えた上から目線の読み方が、最終章で打ち砕かれた。こう来たか、と。最終章で読者は、元山が見つめたアレを、元山とたっぷり同じだけの時間をかけて見つめることになるだろう(アレの存在は小説技法としてはやや反則な気もするが、圧倒的な効果があるのは事実だ)。
そして、ことここに至って、読者は知ることになる。本書が回顧形式で書かれた理由を。大学時代のサークルに賭ける、あの熱病のような思い。それをリアルタイムのように見せたあとで、改めて現在から眺める、その理由を。軽い話の筈だったのに、ベタなマンガの筈だったのに、最終章には泣きそうになった。本書は学生のための小説ではなく、学生だったことのある大人たちへの小説なのだ。
絲的メイソウ・サバイバル・炊事記絲山秋子/講談社文庫
10/08/21


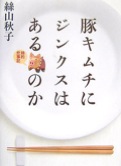
ときどき、「えっ、こんな人だったの?」と驚かされることがある。
たとえば、かなり古い話になるけれど、初めてラジオで中島みゆきのDJを聞いたときには驚いた。わかれうただのうらみますだのを歌う野太い声の女性が、こんなファンキーなキャラだったとは。それは作家でも言えることで、東野圭吾の「あの頃ぼくらはアホでした」を読んだときには、これがあのミステリを書いた人なのかと目を疑ったし、京極夏彦が「どすこい」を出したときも同じ衝撃を受けたものだった。
そして絲山秋子である。
失礼ながら系統的に作品を拝読したわけではないので、あたしにとって絲山秋子は「芥川賞作家」というイメージしかなかったのよ。芥川賞つったらアレですよ、ブンガクですよしかもブンガクに純とかついちゃうわけですよ。そういう人のエッセイなんだから、コムズカしいこと書いてんのかな、それともゲイジュツ的とかゼンエー的とかヒヒョウ的とかだったりするのかな、あるいは説教?みたいな先入観があったわけ。 したらばさ。読みながらあたしの脳裏に浮かんでしょうがなかった思い。
「芥川賞とったほどの作家が、なぜここまで身を削って笑いに走る?! アンタは何かの罰ゲームをやらされる若手芸人かっ!」
「絲的メイソウ」は身辺雑記。メイソウっていうからてっきり瞑想だと思ったのだが、これはどう読んでも迷走。好みの男性はハゲだとか、男はどうすればモテるかとか、寝言の話とか、喫煙話とか。内容はともかく一回分ぜんぶを五七調で書くという「何がやりたいんだ」と笑うしかない項もある。一番笑ったのは「自分の取り説」だ。〈各部の名称〉や〈上手な使い方〉の項に腹筋つるかってほど笑った。「恋のトラバター」に至っては、38歳での恋をリアルタイムレポートしてくれるんだから驚いた。
読んでいて「こういうの、読みでがあるな」と思ったのが「アンチグルメ体験」だ。「この食べ合わせは不味い」というのを探すためだけに、いろんな食材の組み合わせを自宅で試してみるというだけのレポートなんだが、これがもう、おかしゅうて楽しゅうて。楽しいだけでなく、その味の描写がいたく想像力を刺戟する。このあたりの描写力はさすがだなあ、と。そしたら案の定というか何というか、「絲的炊事記 豚キムチにジンクスはあるのか」は、徹頭徹尾、自炊エッセイである。
罰ゲームか、と思ったのはこれだ。何が悲しゅうて自分から「真冬に冷やし中華を食べる」なんてことをせにゃならんのか。なぜ何の見返りも無いのに、経験上かなりの確率でアタってしまう牡蠣を敢えて食べるのか。もちろんおいしい料理が出来る項もあるんだが、読んでてインパクトが強いのはやはり不味い方である。そうそう、「絲的メイソウ」で出てきた恋バナと同じ相手かどうかは分からねど、ここにも恋愛話が出て来る。惚れた相手から卵を貰うという、「どう考えても恋愛対象と思われてないぞそれは」というエピソードはまるで一遍のおもろかなしい小説を読んでるかのよう。
そして更に罰ゲーム度が増したのが「絲的サバイバル」だ。自腹で一人キャンプをして、そのレポート。ホントにもう、何が悲しゅうて天下の芥川賞作家が、薪を運び寝袋で寝てヘッドランプの灯りで原稿を書かねばならんのか……(滂沱)。そしてなぜ、そんな企画を自分から言い出す……? 分からん。ブンガクシャの考えることは分からん。分からんが、でもなんか、妙に楽しそうだったりして。講談社の庭でキャンプするってな「は?」という項もあるし、超恐ろしい霊体験をしてマジ死ぬんじゃねえかって項もあるにはあるんだが、薪の上に鉄網載せて、エリンギ焼いて食べたいな、なんて思ってしまうのだ。氷の上のカタツムリを見たくなるのだ。たとえ一泊でも世俗を離れるって、いいな、と感じてしまうのだ。とてもアウトドア心をそそってくれるエッセイ集。でも普通は自分からは言い出さねえよなあ、やっぱ。
福家警部補の再訪大倉崇裕/東京創元社
10/07/21

実に映像的! ドラマになったのも頷ける。コロンボや古畑というヒット作の先例もあり、このパターンの倒叙モノってだけで安定感抜群なんだが、伏線の妙が抜群で、読みながら「そこかあ!」とのけぞること多々あり。ただ、福家警部補のキャラが「一見刑事には見えない」ってことで、毎回毎回プチ水戸黄門的(権威という意味ではなく、まさかそうとは思わなかったという脱力系)展開があるのが、続けて読むとやや面倒くさくも感じるんだが……単発なら気にならないんだけどね。ここらでちょっと違った趣向の展開があってもいいかな、とは思いましてよ。
今回、「あ、そうか」と膝を打ったのは後書きだ。コロンボ同様、本書では福家の内面描写をしていないという話。これを著者本人に言われるまで気付かなかったあたりが我ながら悔しいのだが、なるほど確かにその効果たるや大きなものがある。たとえば東野圭吾の加賀恭一郎も、倒叙に限ったものではないけれど、内面描写をしないことで成功した例だし。内面を描写しちゃうとシリーズとして同パターンの話を続けられなくなってしまう、というのは考えればわかることで、長く続くシリーズには続かせるだけの工夫があるのだなあと感心した次第。手法といい、本格としてのレベルといい、コロンボや古畑が好きという人には安心して薦められるシリーズだ。
「マックス号事件」
豪華客船の中で起きた殺人事件。マヌケな理由でそこに居合わせた福家が、現場の不自然な状況に気付く。これが面白いのは、福家より先に犯人が自分のミスに気付くところ。
「失われた灯」
人気脚本家が骨董商を殺し、放火。手がかりはすべて燃えてしまったかに見えたが……。ああ、これは小説じゃなくて映像で見たいよ! 映像で見た方が「おお!」と思えるような話。ただしかし逆に映像にしちゃうとあからさまになっちゃうかな?
「相棒」
ベテラン漫才師の片割れが二階のバルコニーから転落死。事故か自殺に見えたものの……。これは謎解きよりも物語としての背景がすごく切なくて印象的。雨という天気は小道具としても必要なのだけど、それ以上に物語全体を彩るひとつの悲しい演出になっている。
「プロジェクトブルー」
おもちゃ会社の社長が恐喝者を殺した。しかしその計画は意外なところから破綻して……。っていうか、福家、趣味広すぎじゃないのか。「相棒」では演芸にめっちゃ詳しいところを見せたかと思えば、こんどは特撮かよ! しかもかなりマニアックだし。こんな変な個性を出しておいて内面描写がないんだから、そりゃやっぱ惹かれるわなあ。
