何か文句があるかしらマーガレット・デュマス/創元推理文庫
10/09/24 格納先:タ行の作家

うきゃあ、面白い面白い! こういうシリーズを待っていた!
ヒロインは三十代で、小さな国なら一国賄えるほどの財産を持つセレブのチャーリー。道楽の演劇修行でロンドンを訪れ、そこで出会った男性ジャックと恋に落ち、電撃結婚。ダンナ様連れで地元のサンフランシスコに帰ってきたのだが、新居が決まるまでと泊まった高級ホテルのバスルームに見知らぬ女性の死体があった。そして彼女が所属する劇団にも災難が相次ぎ、そんな中で夫の意外な面が出て来て──。
本書を読んだときのワクワク感と興奮は、イヴァノヴィッチの『私が愛したリボルバー』を初めて読んだときの興奮に似てる。それまでになかったヒロイン像、テンポがよくてしゃれた会話、個性的なキャラクタ、ぶっとんだ設定、けれどリアルな生活感と人間関係があって、ストーリーは疾走感に、読後は爽快感に満ちた物語。ご都合主義上等!
等身大のヒロインが身近な場所で頑張る話も大好きだが、こういう桁外れの金持ちが金持ちならではの力を使って問題に取り組むというのもまた爽快で面白い。そして金持ちというのは、問題解決の手段に金銭的な制約を受けないというだけであって、彼女の価値観や考え方や感覚はとっても身近。そのバランスが絶妙だからこそ、読者は「わかるわかる」と頷く部分と「わはは、すげーな」とひっくり返る部分の両方を楽しめる。
チャーリーは買い物好きで、料理が嫌い。好きなものを好きなレストランで好きなときに食べられる財力があるんだから、料理なんてする必要がなぜあるの、てなもんだ。金さえあればあたしもそう思うよ。
その一方で、結婚したら次は子ども、と当たり前のように言う友人にカチンと来たり、夫が妻をコントロールしようとしたり命令したりすれば侮辱と受け取るという、現代女性として思わず納得の感覚を持っている。このあたりも読者の共感を呼ぶところ。
まあ、その向こう見ずさで誘拐犯を追いかけたりしてちょっとピンチになったりもするんだが、そこはそれ、お約束だしね。それに決してバカではないので、状況を見て自分でコントロールする術も知っている。自分に非があることはちゃんと認め、改めるよう努力する。三十代の大人の女性だもの。それがまた心地良い。
チャーリーを巡る登場人物たち──夫のジャックはもちろん、叔父のハリーや友人のアイリーン、ブレンダ、サイモン、ボディガードのフランク、家政夫(でいいのかな?)のゴードン、夫の同僚のマイク、ヤハタ警視など、それぞれも個性的なだけでなくプロフェッショナルなのがいい。仲良し友達でわいわいというだけじゃなく、皆自分の分野に一家言持っている。キャラ小説と言って言えないことはないが、そのキャラが自分の生活をきちんと持ってる大人なのがいいんだよね。
そして肝心のミステリ部分も(本格ではないので推理は無理だが)サスペンスと意外な展開に満ちていて飽きさせない。これは楽しみなシリーズが登場した。これまで創元推理文庫のシリーズでは、ジル・チャーチルとコリン・ホルト・ソーヤーが不動のTOP2で第3位にエレイン・ヴィエッツがつけてたんだが、正直、ヴィエッツを抜いたね。追いかける。断固追いかけるぞこのシリーズ。
メグル乾ルカ/東京創元社
10/09/23 格納先:あ行の作家

おお、ステキな連作短編だ。ファンタスティックで、でもリアルで、ちょっぴり怖くて、そして最後は暖かくて。
物語の始まりはどれも、大学の学生部。ユウキという女性職員が、バイトを探しに来た学生に「あなたはこれよ。断らないでね」と勝手にバイト先を指定する。仕方なくバイト先に赴いた学生たちを、不思議な奇跡が待っている──というお話。
通夜の夜に遺体のそばで一晩過ごす「ヒカレル」、病院の売店での商品整理をする「モドル」、飼い主の旅行中に飼い犬に餌をやる「アタエル」、雇い主が作った豪勢な料理をただ食べるだけの「タベル」、そして庭木の冬装備をはずす「メグル」。
「ヒカレル」はホラーテイスト、「モドル」はミステリ、「アタエル」はサイコサスペンス、「タベル」はファンタジー、「メグル」は幽霊譚、というふうに分けようと思えば分けられる。けど細かくジャンル分けせずとも、ざっくりと「不思議で怖くて暖かい話」と表現するのが一番いいかも。
ただ特記しておかねばならないのは、いずれも奇跡の物語であるにも関わらず、登場人物や物語の設定は実に地に足の着いたリアルなものであるということ。「ヒカレル」で描かれる、ひとりで死ぬ事の寂しさ。「モドル」「タベル」に登場する病気の現実。「アタエル」で明らかになる家族の問題。「メグル」で描かれる理不尽な運命。
詳細を書くとネタバレになるので書かないが、誰もが向き合う可能性のある〈不幸〉に、ときには当事者として、そしてときにはちょっと関わるだけの間柄として実際に向き合ったとき、どんな葛藤を抱き、それをどう解決して行くかというところに本書の眼目はある。ファンタジックな演出は、それを後押しするに過ぎない。根っこがリアルで、ディテールが具体的だからこそ、ファンタジックな展開も生きる。特にお薦めは「モドル」。これは確か推理作家協会だか本格ミステリ作家クラブだかの年鑑にも捕られてたんじゃなかったかな。最もファンタジィ風味の少ない一編。
個人的にのけぞったこと。5つの短編のうち3つに病気のエピソードが出てくるのだが、そのうち2つが、あたしのごく身近にいる人と同じ病気だったのだ。ひとつはメジャーな病気だけど、もうひとつはマニアックというかマイナーというか、けど難病指定されてる知る人ぞ知るって病気で。まさか自分に近いところにある病気が続けざまに連作短編集に出て来るとは。読む側として感情移入も一入。
それが奇跡で治るものよりは、治らないという現実にちゃんと向き合うものの方が、個人的には読んでて納得できたな。ま、それは個人的な事情だけど。
魔法使いの弟子たち井上夢人/講談社
10/09/22 格納先:あ行の作家

あたしが最も読んでて辛い話、それは「自分ではどうしようもないこと、自分には何の責任もないことで、理不尽に周囲から排斥され、虐げられる」という話だ。小公女とかさ。アンネの日記とかさ。橋のない川とかさ。こういうのって本人の自助努力だけでは解決できず、周囲や環境や状況が何か変わるのを待つしかない。だから読んでて辛い辛い辛い。そして本書にも、そういう要素がある。
本書では、凶悪な伝染病から奇跡の生還を果たすも、後遺症として超能力を得てしまった3人が登場する。千里眼になった京介。念動力を得ためぐみ。本当は九十代なのに三十代の体に若返った興津。
まずめぐみは、致死のウィルスを運んだ張本人として近所の人から人殺し呼ばわりされる。実家も焼かれている。これはね、嫌な話ではあるけど、分かるのよ。いくら本人にその自覚がなかったとはいえ、そのせいで病気を移され家族を亡くした人にしてみれば、どれだけ悔しく、腹立たしいか。だからめぐみ本人も、人殺しである自分というものを可哀想なほどに自覚してる。
でも、問題はこの先。超能力を得た彼らは、最初は面白がられる。けれどある事件がきっかけで、世間は彼らを危険なものと認識し、恐れ、──そして狩ろうとするわけだ。
でも、小公女やアンネの日記とは大きく違うところがある。それは、彼らの超能力が半端なくすごいこと。従来の超能力の概念を超えちゃうくらいの、万能っつかスーパーマンつか、早い話が彼らは誰が攻撃してきても圧倒的に強いのよ。彼らが本気で戦おうとするなら、絶対負けないのよ。これは超能力なんてもんじゃない。魔法。だからタイトルが魔法使いの弟子たち。
自分たちには特殊な能力があって、それは別に望んで得たものではなくて。だから自分なりにその力に折り合いをつけ、生きていく方法を探る。特にめぐみの決意や努力は涙ぐましいほど。だけどその能力故に人を巻き込み不幸にしてしまうという事実があって。ここの葛藤が読みどころ。
そんな状況で、どうすれば平和裏にすべてを解決することができるのか。読者は彼らの視点に立ってるから状況がわかるし感情移入もできるけど、世間はそうはいかない。本書では警察ってのがすごく頭の固くて面子にこだわる勢力として描かれてるけど、同じ設定で今野敏あたりが警察視点で書くと、きっと警察の行動に理があるように思えて来るだろう。それくらい信じられない能力を彼らは持ってるわけだから。それは即ち、自分がこの場にいたらやはり彼らを恐れ、異端視するのではないかという、自分に対する不信すら生む。
超能力のすごさ、それを発揮するシーンの盛り上がり、科学ミステリとも言える仕掛け、アクションシーンの臨場感など、もうページをめくる手がとまらない。そんなエンタメ満載のベースに、人から異端視されるという悲しみが漂う。そこがいい。
このラストは賛否両論あるかもしれないが、あたしはアリだと思う。てか、このラストで救われた気持ちになった。と同時に、もう一度恐怖が甦ってきた。救いと怖さと余韻のある、巧い終わり方だと思う。
あ、救いと言えば、(もちろんいろんな思惑があるとは言え)彼らに近い場所にいた病院関係者だとか、職場の人たちだとかが、彼らが人類を超えた能力を持ったと分かってからも彼らを理解し、助けようとしてくれたことも挙げておかねば。そういう理解者の存在は、「理不尽に辛い話なんか嫌だよ」というあたしのような読者にとっても助けになった。
ふたりの距離の概算米澤穂信/角川書店
10/09/22 格納先:や・わ行の作家

古典部シリーズ最新作。
校内マラソン大会、そのゴールまでに奉太郎は古典部のとある問題を解決する必要に迫られていた。春先に古典部に仮入部した大日向友子が、前日、いきなり入部しないと言い出したのだ。別に入らないなら入らないでいいんだが、ちょっと釈然としないことがある。学年別クラス別に時間差スタートをとるマラソン大会で、奉太郎は時間と距離を調整しながら関係者に話を聞く──。
基本はマラソン大会のスタートからゴールまで。その合間に過去のエピソードが挿入される、いわば『夜ピク』古典部バージョンとも言える設定。
回想シーンで展開されるプチ日常の謎(新歓での製菓研究会の謎や、喫茶店の店名などなど)も、「どうだ!」というケレンがまったくなくて、とてもスタイリッシュに展開される。基本的に、あまり熱くならずサラリと躱す感じの推理。これもいつもの通り。
でもってこのコーコーセーたちがもう、かわゆーてかわゆーて。
米澤作品の高校生ってのは、どの作品でもそうなんだけど、「本当の自分」「理想の自分」「他人にこう見られたい自分」の3つの中で揺れてる感じが、もう若さならではでタマランものがあるのよ。この感覚、大人になってからも覚えてて、それをこうして青さ満載のキャラクタにできる(しかもその自意識をさらっと実にスマートに表現している)ってのは、すごいなあ。
でもってその青さ、若さというのが、物語の核であり同時に謎を謎たらしめている要素でもあるわけで。だってさ、新入生が部活に入部するとかしないとか、自分が他人にどう見られているかとかって、まあぶっちゃけ四十路の目からみると、どーでもいいことだったりするんだよね。でも、そんなどーでもいいことが生活のすべてになっちゃうのが高校時代なのだよ。でもって、そんなどーでもいいことを、自分の美意識に合わせた形で解決しようとしちゃうのも高校時代なのだよ。そういうことをいちいち思い出せてくれるもんだから、おばちゃんたまりません。
なんかぜんぜん内容の説明になってない気もするが、謎そのものが浮上する過程つーか、そのテクニックも著者の魅力のひとつだと思うので、先入観なしに読んで戴いた方が良いかと。若い読者には「自分に近いのに、でも決定的に自分とは違うかっこよさへの憧れ」を、中年以上の読者には「若いって渦中にいるときはわかんないけど、実はけっこう苦いよね」という思いを味わえるシリーズだと思う。
それはさておき、その喫茶店のネーミングセンスは如何なものかと。
死ねばいいのに京極夏彦/講談社
10/09/22 格納先:か行の作家

何年前かなあ、テレビでダウンタウンの浜田雅功さんが、他人に向かって「死ねばいいのに」と言っているのを聞いたときにはギクリとした。そしてとても嫌な気持ちになった。ギャグだと、冗談なんだと、言われる側も笑ってるんだと、重々承知していても、それでも「死ねばいいのに」なんて言葉、使って欲しくないと思った。ノリで使って笑って済ませられるような、そんな軽い言葉じゃないだろ?
以来、「死ねばいいのに」はあたしの中で、〈日常生活で絶対に口にしたくない言葉ランキング〉の1位2位を争う位置にある。ブログなどで「死ねばいいのに」という言葉をジョークとして使ってる人を見たら、「ああ、この人はこの言葉を抵抗無く使えるタイプの人なんだな……」と感じ、ちょっと印象が変わったりもする。まあ、個人的な勝手な見方ですけどね。
それほど嫌いな言葉が書名になるってアンタ、在庫の確認をするため書店に電話をかけ、電話口で「死ねばいいのに」「死ねばいいのに」と繰り返すたびにどれほど心が荒んだことか。
本書はインタビュー形式。ある女性が死んだあとで、その女性と関わりのあった人のところにケンヤという無作法な若者が現れ、その死んだ女性のことを教えてくれ、と言う。視点は、いきなりケンヤに訊かれた側(インタビュイー)の方で、だからまずケンヤという頭の悪そうな若者に対して警戒するし、なんで自分にそんなことを訊くんだと不審に思ったりもする。
けれど、自称「頭が悪い」ケンヤの素朴な質問に答えるうちに、インタビュイーたちの言い分がいかに空虚で身勝手なものなのか、その実態が丸裸にされて行くのだ。そしてその先には、思わぬ真相が待っている。
仕掛けとしては特に凝ったものではない。ひとつのパターンの繰り返しでもある。けれど読まされてしまい、「巧いな」とつくづく感じてしまうのは、やはり京極夏彦だからとしか言いようが無い。ケンヤの役目(の一部)は京極堂の憑き物落としに等しい。物事を飾らず誤摩化さず、シンプルにシンプルにつきつめていけば、真実が見えてくるのだ。グサグサ来る。ホントにグザグサ来る。テーマがあまりにも前面に出過ぎで分かり易過ぎるのが気になるが、圧倒的な文章の力がそれをむしろ美点に転化している。
ケンヤの決めセリフ「死ねばいいのに」には、「そんなに辛いなら死ねばいいのに、死なないのは死なないでいる理由があるからでしょう? それが何なのかわかるでしょう?」という問いかけもしくは糾弾がある。バラエティ番組やブログなどで目にする「死ねばいいのに」は、「私にとってあなたは目障りだからいなくなればいいのに」というエゴでしかない。けれどケンヤの「死ねばいいのに」は甘えずに自分をもう一度見つめるという自助努力だ。そこが決定的に違うのである。
甘えたことを考えたり、うまくいかないことを他人のせいにしたくなったら、再読しよう。そしてケンヤに喝を入れてもらおう。
屍の命題門前典之/原書房
10/09/19 格納先:ま行の作家

うっわああ、すっげえチカラワザ!! 豪腕っつーか無理矢理っつーか、いやあ、よくこんなこと考えたなあ。なんかもう、笑ってしまうほどにチカラワザなんだもん。つか、実際に笑っちゃったもん。<誉めてます。
亡き大学教授の山荘に集まった6人。もてなす側の教授夫人が参加できなくなったため、6人だけで過ごすことになる。教授の趣味だった昆虫標本を飾った部屋や、屋敷の前に設置されたギロチン台など、どうも気味が悪い。そして雪が積もり、電話は通じず、車のタイヤは切り裂かれ、“吹雪の山荘”にて次々と人が死に──そして誰もいなくなった……。
これでもかーーーっ!と言うくらいの典型的な“吹雪の山荘”モノ。足跡の無い雪密室ありぃの、切断された死体ありぃの、伝説が伝わる湖ありぃの、奇妙な館ありぃの、そして誰もいなくなりぃの。「まだ来るか!」と思うほど、畳み掛けるような本格のガジェット。いやもう、お好きな人にはたまらんのではないかしら、これ。
でもってこのチカラワザぶりには……わははは、だめだ、やっぱ笑いが漏れてしまう。著者の意図はさておいて、これは「ケレンたっぷりの本格ミステリ」でしょうかそれとも「バカミス」でしょうかというアンケートをとったら、五分五分か、もしかしたら「バカミス」の方が多くなるんじゃないかしらん、というくらい微妙なラインなのよね。絵面を想像するとスゴいんだもん。特に、雪のつもった庭で殺されて、周囲に足跡がなかったという一件の真相なんて、その状況をビジュアライズしたらかなりのギャグ映像になるよ。死体移動の真相も……ものすごい状況なんだけど、絵を想像すると「いや、ないって! それはなんぼなんでも無理だって! ちょっと落ち着け!」と探偵役にツッコミを入れてしまった。いやあ、演出によってはとてつもなくホラーなシーンになるところなんだけど、恐怖感を感じる前にツッコミを入れてしまうってのは、やっぱ、バカミス寄りってことかと。あ、サプライズは充分ですよ。ホントに驚いた。いろんな意味で。
大掛かりなトリックというか、チカラワザというか、豪腕というか──そういうトリックものが好きな人は読み逃しちゃいけません。あと、バカミスが好きな人も。でもね、見た目のケレンを除いて真相の骨格だけ見ると──ものすごく緻密に練られてるんだよ、これ。単なる豪腕バカミスってだけでは、ないようですぜ。
蝦蟇倉市事件(1)(2)伊坂幸太郎他/東京創元社
10/09/19 格納先:アンソロジー
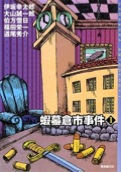
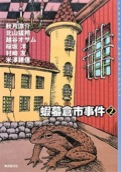
風光明媚にして歴史ある地方都市、蝦蟇倉市。ここはなぜか不可能犯罪が頻発する都市でもあった──。そんな蝦蟇倉を舞台に書かれたミステリの競作アンソロジー。まえに祥伝社が同じような企画で「まほろ市の殺人」を出したけど、物語同士の相互リンクはこちらの方が楽しめる。何がいいって、カバー裏の地図がいいよ!
執筆陣が1巻が道尾秀介、伊坂幸太郎、大山誠一郎、福田栄一、伯方雪日。2巻が北山猛邦、桜坂洋、村崎友、越谷オサム、秋月涼介、米澤穂信。
どれが良いかってのは読者の好き好きだけど、まずいきなり道尾秀介「弓投げの崖を見てはいけない」にヤラれた。ドラマチックにしてテクニカル。意外性に驚き、ラストでまた驚き──でも一番驚いたのは巻末の著者の言葉を見たときだ。え、あたし何も疑問に思わずそのままスルーしちゃったけど、あ、そうか、幾通りか考えられるパターンがあるんだ。それからは読み返しいの地図見いの。
そして次の伊坂幸太郎「浜田青年ホントスカ」で、いきなり「弓投げの崖を見てはいけない」に出て来たちょっとしたエピソードとのリンクがあったりして……こういうのって、つまりは遊び心なんだけど、それがいいよなあ。そうそう、「浜田青年ホントスカ」で印象深かったくだりをひとつ挙げておこう。「不可能犯罪って何ですか」という問いかけに続いて、こんな会話がある。
「普通では不可能としか思えない犯罪のことですよ。鍵の閉まった部屋で誰かが殺されていたり、鍵の閉まったトイレで誰かが死んでいたり、鍵の閉まった納戸の中で五月人形が壊れていたり、そういった不可能状況での犯行を主に指します」
「それだけ鍵が関係してるなら、鍵屋の仕業だと思いますよ」
吹き出してしまった。わははは、そうだよなあ。2巻の越谷オサム「観客席からの眺め」にも、本格ミステリの設定自体を揶揄するような、あるいは非難するようなくだりがある。そうかと思えば、2巻の桜坂洋「毒入りローストビーフ事件」のような「パズルのためのパズル」に特化したような作品もある。これぞ本格という感じの大山誠一郎「不可能犯罪係自身の事件」(ここに登場するキャラクタはこの後に引き継がれて行く)、もはやバカミスだと笑ってしまった伯方雪日「Gカップ・フェイント」、この幅の広さもアンソロジーの魅力だ。
そして掉尾を飾る米澤穂信「ナイフを失われた思い出の中に」で、「あっ」と飛び起きた(寝転がって読んでたんです)。うわあ、こんなところで再会できるとは! ここに出て来る登場人物は、あたしが最も好きな米澤作品の人物なのだ。シリーズ物ではないと思ってたので、まさかこんな嬉しいサプライズがあるとは思わなかったよ。この一編を読めただけでも2巻を買う甲斐はある。そうか、今はモンテネグロなのだなあ……。
キケン有川浩/新潮社
10/09/19 格納先:あ行の作家

ああ、やられた。これにはやられた。
キケンとは、成南電気工科大学のサークル、機械制御研究部のこと。即ち、機研。新入生の元山と池谷が二回生の上野から勧誘され、入部を決めたは良かったが、このサークルの上級生はまさに「キケン」だった。もちろんこちらは「危険」の方。
そこから1年に渡るキケンでの熱い熱い青春が回顧形式で語られる。春は新歓、初夏は恋、秋は学祭、そして冬の終わりにはロボット相撲。ひとつひとつはホントにこの著者らしく、善くも悪くもマンガなのよ。理系大学の実作サークルの、ある一面をデフォルメして面白く仕立てて。登場人物にも個々それぞれに一定の方向付けがなされているという、つまるところ「多面的で不確定な人間」ではなく、あくまでも「役割を持ったキャラクター」。それをわざと──というか、最初からそういうものを書きたくて、確信を持って書いている、という作風。テンポ重視で、軽くて、ボケとツッコミがあって、キャラが立ってて、アクションもあって、トラブルに出会っても必ず最後は解決するのがわかってる安心感もあってという、ホントに爽やかなマンガの王道なのね。
一昔前までは「マンガみたい」というとそれは悪口だったのだが、今やそんなふうに解釈する人もいないだろう。むしろ上に書いたようなマンガならではの魅力や個性といったものをテキストだけで十全に再現するというのは至難のワザだ。本物のマンガである挿画も一端を担っているとは言え、本書はまさに「読むマンガ」を体現している。映像、音、迫力、疾走感──それらを文字だけで作り上げ読者の五感に響かせている。相当の筆力と構成力がなければできないこと。
ただ……シンプルでベタなストーリー展開は、楽しいけれどそれだけだよな、と思いながら読んでいた。面白いし笑っちゃうし読み出したら止まらないテンポもあるけど、でも、話としてはよくある種類のもんだよな、と。ところが。そんな斜に構えた上から目線の読み方が、最終章で打ち砕かれた。こう来たか、と。最終章で読者は、元山が見つめたアレを、元山とたっぷり同じだけの時間をかけて見つめることになるだろう(アレの存在は小説技法としてはやや反則な気もするが、圧倒的な効果があるのは事実だ)。
そして、ことここに至って、読者は知ることになる。本書が回顧形式で書かれた理由を。大学時代のサークルに賭ける、あの熱病のような思い。それをリアルタイムのように見せたあとで、改めて現在から眺める、その理由を。軽い話の筈だったのに、ベタなマンガの筈だったのに、最終章には泣きそうになった。本書は学生のための小説ではなく、学生だったことのある大人たちへの小説なのだ。
Nのために湊かなえ/東京創元社
10/09/18 格納先:ま行の作家

卓越したストーリーテリングでぐいぐい引っ張られた、としか言いようが無い。
実は読み終わってから落ち着いて考えると、なんか放り出された感はあるし、張りっぱなしで回収されてない伏線はあるし(それとも伏線じゃなかったのかしらん?)、事故だか事件なんだか明確になってない箇所はあるし、なんかこう、落ち着くべきところに落ち着いてない状態で終わってしまったような、そんな釈然としない気持ちは残るのよ。ただ読んでる最中は、展開が気になってどんどんページをめくらされた。途中でやめられなかった。行き着く先を見たい、と強く思わされた。その「行き着く先」が気に入るかどうかは読み手の好みの問題。
物語は、あるセレブな夫婦の自宅マンションで殺人事件が起きたところから始まる。死んだのはその夫婦。その場にいたのは夫婦の友人であり、そこに招かれていた杉下希美と安藤望、レストランの出張サービス係・成瀬、そして犯行を自供した男、西崎。彼らの事情聴取が第一章だ。
そして時間はいったん未来に飛んだ後、過去へ戻る。そして読者は驚かされることになる。もともと友人だった安藤と杉下以外は、お互い大きな関わりはないとされた関係者たちの、思わぬ関係が徐々に明らかになるから。どこまでが計画だったのか。その目的は何だったのか。誰が知っていて誰が知らなかったのか──章が変わるごとに提示される新事実には、その都度「わあ」とのけぞり──そして、ワクワクした。「どうだ!」とばかりにこれ見よがしに新事実を明かすのではなく、ごくごく淡々と、当たり前のように時間を遡って「企みの過程」を描写する、そのさりげなさ。さりげないが故に、著者の「にやり」が見えるようで実に楽しい。構成のマジシャンと呼ばせて戴く。
ただ、彼らの過去は、決して楽しいものではない。この物語に登場する若者たちは皆、ここではないどこかへ行きたいと思っている人たちばかり。逃避という意味ばかりではなく、もっと前向きに、そしてもっと切実に。足掻いている、と言っていい。その足掻きと、テクニカルな構成が実に巧くマッチしている。“Nのために”のNとは、誰の(あるいは何の)ことなのか、幾通りもの解答を楽しまれたい。
それにしても──子供時代が決して幸せとは言えなかった彼らが足掻いて足掻いて、感情移入させるだけさせといて、その結末がこれかと思うと……話は冒頭に戻るが、「落ち着くべきところ」に落ち着かせて欲しかったよなあ、やっぱり。
蔵書まるごと消失事件イアン・サンソム/東京創元社
10/09/18 格納先:サ行の作家

アイルランドの片田舎タムドラム。図書館司書として採用され、この地を訪れた青年イスラエルを待っていたのは、なんと図書館入り口に張られた閉鎖のお知らせ。慌てて役場に行ってみると、代わりに移動図書館をやれと言う。バスはおんぼろ、住人は変人、役人は強引。「思ってたのと違う…」とぼやきつつしぶしぶ受けたイスラエル。しかし移動図書館に載せる予定の本を運ぶべく旧図書館に行ってみると、なんと1万5千冊の蔵書が一冊残らず消えている! 移動図書館巡回開始日は既に告知済み、刻々と迫るタイムリミット。果たして本は見つかるのか?
わはははは、楽しい、楽しい! アイルランドが舞台の小説といえば石持浅海の「アイルランドの薔薇」が思い浮かぶが、同じ国の話とは思えない。アイルランド人がこの話に出て来るような人ばっかりだったら、「アイルランドの薔薇」はきっと永遠に解決しなかったであろう。それくらいヘンな人たち。おまけに主人公のイスラエル君がもう、ヘタレでヘタレで。うわははは。
ただそのヘタレぶりが、けっしてただの笑わしではなく──なんかちょっと切なくなったりもするんだよね。彼は「こうありたい自分」と現実の自分の乖離に戸惑い、悲しみ、自分をごまかそうとし、でもごまかしきれず、足掻いている。見知らぬ街で見知らぬ風習の中に放り込まれようが、なじんだロンドンの街にいようが、きっと彼はどちらでも異邦人なのだろうなと読者には分かってしまうのだ。けれどそれがユーモラスに描かれているのが、いい。必要以上に重くなりすぎず、でも小さな刺を読者の胸に残す。
そう思って読んでいくと、この真相も──決して目新しい謎解きではないんだけども、図書館が閉鎖されるような田舎町の、おそらくは開発からも取り残されているのであろう田舎町ならではの悲しさというのが浮かび上がってくる。特にその「犯行」の様子を想像するとね…。
という「悲しみ」を底辺にたたえつつも、いや、でもやっぱ楽しいのよ。特に移動図書館と地域住民の関係にはいちいち笑った。返す本を木の下に置いとく習慣って何なのそれ。返却期限切れの本を当たり前のように家に置きっぱなしにするなよ! 延滞金という制度があってもやはり図書館ユーザーとは期限を守らないものなのか。司書の苦労がしのばれる。
次の巻ではいよいよ図書館業務が開始されるんだろうか? おもしろおかしい住人たちとの関係はどうなるんだろう? また楽しみなシリーズの登場だ。
カッコウの卵は誰のもの東野圭吾/光文社
10/09/18 格納先:は行の作家

おお、久しぶりのスポーツ物! というか「鳥人計画」以来のスキー物!(<「ちゃんれじ?」は含みませんことよ) これがバンクーバー五輪直前に出るあたり、商売人よのう。
往年の名スキーヤーで現在は引退している緋田。今は娘の風美がスキーで頭角を現し、関係者の期待を集めている。そこに現れた一人の男。彼はスポーツ選手の遺伝子を研究しており、ぜひ父娘の遺伝子を調べさせて欲しいというのだ。けれど緋田には、それをどうしても認めるわけにはいかない理由──ある「秘密」があった。それは──。
遺伝子を調べさせたくない理由ってのは、本書のタイトルをみれば一目瞭然だし、作中でもかなり早い段階で明らかにされるのだが、まあ具体的には触れないでおこう。ただ主人公は、その「秘密」を永遠に守りたいという気持ちの中に、このままでいいのかという気持ちもちょっとある。「秘密」をすべて明かしてしまった方が、もしかしたら娘のためになるのではないか、という気持ちも否定できない。けれどそれを他人に暴かれるとなると話は別なわけで。
本書はその「秘密」が意外な方向に転がって行く過程をサスペンスにしたものなのだが、まあなんつーか、今更ではあるけどとても読みやすい。文章に変なケレンがなくてストレートで、けれどディテールの描写がしっかりしているので、読者は目の前で映像が展開されるような気持ちで読み進んでいける。と同時に、この読みやすさにはもうひとつ理由がある。ここには一面的な“悪者”がいないのだ。
ここに出てくるのは、いわゆる普通の一般市民である。ミステリなら、自分の犯罪を隠すためにあれこれ策を弄したりだとか、殊更自己の利益を追求したりだとかってな人がよく出てくるが、ここに出て来る人物たちは皆、善くも悪くも真っ当な精神と真っ当なエゴを持っている。そこがリアルで、いい。ミステリの登場人物ならこんな行動はとらないんじゃないか、でも現実の自分ならまさにこう動くんじゃないか──そんな行動を彼らはとる。悪いことをすれば罪悪感にとらわれ、謝りたいと思う。人が災難に遭ったと聞けば心配し、被害者の家族を思いやる。そんな真っ当で健全な心の動きがベースにある。だから読んでいて共感できるし心地いいのだ。まあ、その分、真相がやや唐突な観は否めないが。
驚いたことがひとつ。本書で重要なキーとなっているスポーツ選手の遺伝子(ここでは持久力を必要とするスポーツに向いた遺伝子ということになっている)ってのは、はじめは著者の創作だろうと思ってたのよ。あっても不思議はなさそうな、けっこうリアルな創作だとばかり。したらばさ! ちょうどバンクーバー五輪直前にNHKで、スポーツ遺伝子の特集番組をやっていたではないか。もちろん細かいところは違うんだけども、いやあ、あるんだなあ。ますますタイムリー度アップではないか。
