扼殺のロンド小島正樹/原書房
10/08/21 格納先:か行の作家

読み終わって、まず最初に戻った。プロローグをもう一度、確かめながら読む。……うーん、一カ所、どうにも解せないところがあるんだが……あ、そうか、そういうことか……ま、いっか。<いいのか。
と、ちょっと最初と最後のつながりにスッキリしない部分はある(思わせぶりにしつつ整合性をとらなくちゃならないせいか)ものの、本書に出て来る謎はなかなかに強烈だ。なんせアンタ、二重密室の猟奇殺人ですよ。死体はふたつ。腹を切り裂かれ胃腸が奪われた女の死体。そして無傷の男の死体。そのふたつの死体がドアも窓も開かない事故車の中で見つかる。しかもその事故車は施錠された古い工場の中にあった。もちろん凶器も内蔵も車内にはない──。うわあ、なんというケレン! これでもかってくらいの派手な不可能殺人!
となるとエキセントリック且つ超人的な名探偵が出て来て、どろどろした人間関係が云々みたいなふうになるとかと思いきや。謎にあたるのは生活感溢れるごくごく真っ当な刑事たちである。もちろん「名探偵」は出て来るんだけど、そして彼も個性的ではあるし謎も解くんだけど──それでもやはり事件に直接対峙するのは刑事たちなんだよね。でもって個人的な趣味で言うなら、だからこそ良い、と思うのだ。ケレンに溢れた不可能状況でありながら、刑事たちが事件を現実側に引き寄せてくれる。虚構の中に閉じ込めず、人々が日々の生活をおくる現実に広げてくれる。
ただまあ、それを良しとするのは多分に自分の好みの問題であって、この状況・この真相なら、なんぼでもおどろおどろしくできるよなあ、と思わないでもない。横溝ばりの世界を構築することが──あるいは三津田信三的風味に仕上げることが、充分可能。このモチーフ、このトリック……どっちが良かったんだろうと考えると、かなり難しい問題だ。鑑識だの医学知識だのも登場するので、科学抜きには語れないというのはあるにせよ。
謎解きには膝を打った。途中まで作者の術中にはまり「いや、それどう考えても無理だし!」と眉に唾をつけながら読んでいた部分がすべてキレイに整理されたときには、参った、と思った。関係者が少ないので人がどんどん殺されるうちに自然と容疑者があっちかこっちという状況になるのがチトもったいない気はするものの、なるほどこれはトリックメーカーの面目躍如だと感心した次第。
チーム堂場瞬一/実業之日本社
10/08/21 格納先:た行の作家

読むならやっぱり正月か。箱根駅伝を描いたスポーツ小説です。
堂場瞬一と言えばセールス的には中公文庫の「刑事・鳴沢了」のシリーズの方がメジャーなんだろうけど、あたしは断然彼のスポーツ小説のファン。「大延長」や「8年」(いずれもなまもの書評。以下同じ)などの野球小説が白眉だと思うが、3人のマラソンランナーを描いた「キング」(文庫化に際し「標なき道」と改題)や「神の領域」がまた素晴らしい陸上ミステリで、この人の書く陸上物をもっと読みたいなと思っていた。したらば出ましたよ、しかも今回はミステリではなく純然たるスポーツ小説で、しかも箱根駅伝ですよ奥さん!
箱根駅伝なら三浦しをんのヒット作「風が強く吹いている」を思い浮かべる人が多いかも。確かにあれはとっても面白くて、駅伝というスポーツの醍醐味を見事に表現してくれた傑作に間違いは無いけれど、同時に「未経験者ばかりでここまで巧くいかねーって!」と突っ込みたくなるような演出がチト気になった。もしも同じ思いを抱いた人がいるなら、本書「チーム」はお勧めだ。「風が強く吹いている」がスポーツをモチーフにした青春小説だとするなら、本書は純然たるスポーツ小説と言える。
主人公は箱根駅伝の予選会で落ちた中からタイム上位者が集められた学連選抜チームの面々。だから個々のポテンシャルはかなり高い。でもチームとしては急造。ただ駅伝は、団体競技とは言っても他のスポーツとはチームプレイの意味がぜんぜん違うわけで、個々の記録の合計で競うんだから個々の成績が良ければいいはずだ。だったら駅伝の「チーム」って何なの?というのが眼目。
考えてみれば学連選抜って、めちゃくちゃ特殊なチームだよね。予選落ちしたチームから優秀なメンツだけ集めて1チーム作り本選に出場させるなんて、他のスポーツにはないよ。考えた人はすごいと思う。甲子園や春高バレーでもやれば盛り上がるだろうなあ。
閑話休題。この学連選抜というチームを中心に据えることで最も感心したのは、他の大学が「チームのため、部のみんなのため」に「OBの期待を背負って」走るのに対し、学連選抜の選手たちは「自分のためだけに」走ることができるというくだり。この視点は新鮮だった。陸上小説が好きな人にはお勧めですよ。スポーツシーンの描写にかけては右に出る者がいない(とあたしは思ってる)堂場瞬一なので、駅伝そのものの描写はこっちまで息が詰まるぞ!
新参者東野圭吾/講談社
10/08/21 格納先:は行の作家

本人にとっては余計なお世話だろうけど、直木賞をとってから、ちょっと粗製濫造気味?と勝手ながら一方的に心配をしていた。だってさ、過去にお蔵入り(という表現もどうかと思うが)になっていた作品を急いで出したりとか(出したのは出版社だけどさ)、描写はさすがだと思わせるもののラストが妙に浪花節になってて「大衆ウケを狙ったかひがぴょん!」とホゾを噛んだりとかしたもの。でも、本書を読んで快哉を叫んだよ! やっぱり東野圭吾は健在でした。あー、よかった。ホントよかった。
やっぱり加賀恭一郎モノは安心して読める。いや、ちょっと違うな。安心はできるが油断はできないのだ。レベルとしては高値安定、でも読者の足をすくうような、盲点を突くような展開が必ずあるんだから。
刑事・加賀恭一郎はなぜか日本橋に赴任している(なぜか、ってこともないか)。本書は下町情緒豊かなこの古い町でおきた九つの事件を加賀恭一郎が解き明かす連作集だ。加賀モノのパターン通り、視点人物は加賀ではない。まずその町で暮らす人々の様子が描かれ、事件が起き(あるいは起きたことも知らされぬまま)視点人物のもとに加賀が現れる。それが複数続き、周囲の描写により加賀恭一郎という掲示像が示されると言って良い。外枠を塗っていくことで対象の形が見えて来るようなものだ。
そしてこの描写法は、そのまま連作としてのミステリにも適用されている。それぞれ別個の事件を調査・解決しているようでありながら、実は連作が進むにつれ、外枠が塗られることによってひとつの事件の形が次第に見えてくるのである。いやあ、巧い。巧いよ。今更ながらに巧いよ。
以上は技法の話。けれど本書の最大の魅力は、下町というものの描写にある。下町と言えば人情。けれどベタな人情話ではなく、怜悧な何かを覗かせる。日本橋という下町だって今は平成なのだ。江戸情緒が残っていると言っても、江戸ではないのだ。そういう「現代の下町」が実に見事に──読者の中にある虚構としての下町と現実の下町のブレンド具合が絶妙に醸し出されている。それがまたミステリの謎解きに直結するんだからタマりませんわん。
下町という舞台のせいもあるだろうが、過去の加賀モノに比べると、円熟・滋味という言葉が脳裏に浮かぶ。加賀の内面は相変わらず描かれない。しかし、「卒業」では学生で、「眠りの森」で恋をして、「赤い指」で家族というハードルを越えた加賀も、確かに変化しているということが、シリーズ読者には手にとるように分かるのである。
捨て猫という名前の猫樋口有介/東京創元社
10/08/21 格納先:は行の作家

久しぶりだー久しぶりの草平ちゃんの長編だー。おおお、草平ちゃんがケータイ(作中表記はケイタイ)持ってるよ! 仕事にパソコンを取り入れようなんて考えてるよ! でも初登場の90年(19年前!)から変わらず38歳のままだよ! つか、いつの間にか草平ちゃんのトシを超えてしまったのねあたし……。草平ちゃんがあたしより若いだなんて(愕然)。
気を取り直して。元刑事で現在はフリーライターの柚木草平。別居中の妻と娘(小6)あり。ある日、草平が契約している雑誌の編集部に妙な電話がかかってきた。先頃起きた女子中学生の自殺事件は実は自殺ではない、柚木草平に調べさせろと言うのだ。不審なまま件の女子中学生のことを調べ始めた草平は、一風変わった少女と出逢う──。
出て来る女性が軒並み美女で、それに対して飄々と“口説き芸”を見せる草平ちゃんという図式は相変わらず。でも読者は草平ちゃんの身持ちの堅さを知っていて、ホントにそんな関係には絶対ならないって分かってる。女は冴子さんだけ(つか、別居中の奥さんの存在があるのに“冴子さんだけ”って表現もヘンだが)なのが草平ちゃんの魅力なのだよな。
事件そのものはとても後味が悪い。印象的な場面で雨が降るせいか、全編通してずっと雨に濡れているような、そんな湿り気と薄ら寒さがある。ここで起きた事象だけをすくいあげればホントに陰々滅々としちゃうような話なんだけど、そこにいつもの草平ちゃんを配することによってメリハリをつけ、時には和ませるという効果は確かにある。柚木草平というキャラクタの持っている単体としての魅力ももちろん相変わらずなんだが、むしろ物語全体に及ぼす効果の方が強く印象に残る。主人公のキャラクタにはこういう使い道もあるのだ。ただまあ、もて過ぎだよなあやっぱり。わはは。
さて、上で「変わらず38歳のままだよ!」と書いたが、実はシリーズ初期と比べるとその変化ははっきりと見てとれる。初期は軽妙なハードボイルドの中にペーソスを滲ませた、というイメージだったが、本書はハードボイルドの設定を借りた人情話のように感じられることが多かったのだ。著者が時代もの(これがまたいい!)を書いているせいもあるかもしれない。そしてこの変化は、悪くない。著者も読者も年齢層が上がったせいもあるのだろうけど、結構草平ちゃんに似合っていると思うのよ。
さよならドビュッシー中山七里/宝島社
10/08/21 格納先:な行の作家

この著者の名前から「大菩薩峠」を連想しちゃうのは、あたしだけじゃないよなあ?
って、そんなこたあともかく。宝島社のこのミス大賞受賞作である。この賞の受賞作ってえのは、なんつーか、ある意味「一点突破!」てな感じの作品が多いように見受けられるのだが、これには驚いた。なんてオーソドックスな、なんて手堅い青春ミステリであることか。そしてこれがまた実に“読ませる”のだ。これは今年のミステリ系新人の中でもかなり印象が強いぞ。
音楽科のある高校への進学を控えたピアニスト志望の遥。遥の従姉妹で、両親を災害でなくし遥の家に引き取られたルシア。ところが祖父の離れに二人が泊まった日、離れが火災に遭う。祖父とルシアは死んだものの、遥は全身に大火傷を負いながらも皮膚移植で助かったことを喜ぶ両親。けれどもう一度ピアノを弾くには、辛いリハビリが必要だった。それでも前向きにピアノに取り組もうとする彼女の周りで、不穏な出来事が相次ぐ──。
あのね、ぶっちゃけて言えば本格ミステリとしてはツッコミどころ満載なのよ。「不穏な出来事の数々」については、正直なところフェアとは言えない。というか、読者に与えられるデータが少な過ぎるのね。おまけに容疑者が少ないが故に誰が犯人でもさほどの意外性はない。そして最もサプライズを生む筈のある真相が……うーん、これ、本格ビギナーはすごく驚くと思う。でも、ある程度読み込んでる読者は、ものすごく早い段階で(推理ではなく経験から)「これってあのパターンだったりして」と一度は考えると思うのよね。だって状況がホントにお手本のようなパターン分類にはまってるんだもん。
しかし、それでも、お勧めマークがついてる点に留意願いたい。相次ぐ災厄の中にあって、この少女の描写と音楽の描写が素晴らしいのだ。体が自由に動かない、声も体も以前とはまるで変わってしまった──十代の多感な少女がそんな目にあって、それでもいい指導者といい医者に出会い、足掻きながらも自分の存在をピアノにぶつける。圧倒された。特に、杖無しでは歩けない体になってしまった少女がリハビリに励む、そのディテールはすごい。正直なところ、これはあたしも似たようなリハビリや障碍の例を身近で見ているが故の個人的な感情移入が無いとは言えないが、実体験者の身内が読んでも違和感が無い、むしろ「そうそう、そうなのよ!」と感じてしまうほど描写が正確で、なおかつ迫力がある。
そしてその圧倒されるような少女の描写が、本格ミステリとしての弱さを覆い隠していると言っていい。伏線の仕込みは決して巧いとは言えないのに、物語の持つ吸引力のせいで読者は伏線探しをする暇がない。これもまた立派なミスディレクションだ。
じゃあ単なる音楽スポ根青春小説でも良かったかと言えば、そうじゃない。やはりこれはミステリでしか描けない、たとえパターンそのまんまであろうとこのミステリの形でしか描けないテーマがある。そこがいい。お勧め。
絲的メイソウ・サバイバル・炊事記絲山秋子/講談社文庫
10/08/21 格納先:あ行の作家


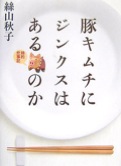
ときどき、「えっ、こんな人だったの?」と驚かされることがある。
たとえば、かなり古い話になるけれど、初めてラジオで中島みゆきのDJを聞いたときには驚いた。わかれうただのうらみますだのを歌う野太い声の女性が、こんなファンキーなキャラだったとは。それは作家でも言えることで、東野圭吾の「あの頃ぼくらはアホでした」を読んだときには、これがあのミステリを書いた人なのかと目を疑ったし、京極夏彦が「どすこい」を出したときも同じ衝撃を受けたものだった。
そして絲山秋子である。
失礼ながら系統的に作品を拝読したわけではないので、あたしにとって絲山秋子は「芥川賞作家」というイメージしかなかったのよ。芥川賞つったらアレですよ、ブンガクですよしかもブンガクに純とかついちゃうわけですよ。そういう人のエッセイなんだから、コムズカしいこと書いてんのかな、それともゲイジュツ的とかゼンエー的とかヒヒョウ的とかだったりするのかな、あるいは説教?みたいな先入観があったわけ。 したらばさ。読みながらあたしの脳裏に浮かんでしょうがなかった思い。
「芥川賞とったほどの作家が、なぜここまで身を削って笑いに走る?! アンタは何かの罰ゲームをやらされる若手芸人かっ!」
「絲的メイソウ」は身辺雑記。メイソウっていうからてっきり瞑想だと思ったのだが、これはどう読んでも迷走。好みの男性はハゲだとか、男はどうすればモテるかとか、寝言の話とか、喫煙話とか。内容はともかく一回分ぜんぶを五七調で書くという「何がやりたいんだ」と笑うしかない項もある。一番笑ったのは「自分の取り説」だ。〈各部の名称〉や〈上手な使い方〉の項に腹筋つるかってほど笑った。「恋のトラバター」に至っては、38歳での恋をリアルタイムレポートしてくれるんだから驚いた。
読んでいて「こういうの、読みでがあるな」と思ったのが「アンチグルメ体験」だ。「この食べ合わせは不味い」というのを探すためだけに、いろんな食材の組み合わせを自宅で試してみるというだけのレポートなんだが、これがもう、おかしゅうて楽しゅうて。楽しいだけでなく、その味の描写がいたく想像力を刺戟する。このあたりの描写力はさすがだなあ、と。そしたら案の定というか何というか、「絲的炊事記 豚キムチにジンクスはあるのか」は、徹頭徹尾、自炊エッセイである。
罰ゲームか、と思ったのはこれだ。何が悲しゅうて自分から「真冬に冷やし中華を食べる」なんてことをせにゃならんのか。なぜ何の見返りも無いのに、経験上かなりの確率でアタってしまう牡蠣を敢えて食べるのか。もちろんおいしい料理が出来る項もあるんだが、読んでてインパクトが強いのはやはり不味い方である。そうそう、「絲的メイソウ」で出てきた恋バナと同じ相手かどうかは分からねど、ここにも恋愛話が出て来る。惚れた相手から卵を貰うという、「どう考えても恋愛対象と思われてないぞそれは」というエピソードはまるで一遍のおもろかなしい小説を読んでるかのよう。
そして更に罰ゲーム度が増したのが「絲的サバイバル」だ。自腹で一人キャンプをして、そのレポート。ホントにもう、何が悲しゅうて天下の芥川賞作家が、薪を運び寝袋で寝てヘッドランプの灯りで原稿を書かねばならんのか……(滂沱)。そしてなぜ、そんな企画を自分から言い出す……? 分からん。ブンガクシャの考えることは分からん。分からんが、でもなんか、妙に楽しそうだったりして。講談社の庭でキャンプするってな「は?」という項もあるし、超恐ろしい霊体験をしてマジ死ぬんじゃねえかって項もあるにはあるんだが、薪の上に鉄網載せて、エリンギ焼いて食べたいな、なんて思ってしまうのだ。氷の上のカタツムリを見たくなるのだ。たとえ一泊でも世俗を離れるって、いいな、と感じてしまうのだ。とてもアウトドア心をそそってくれるエッセイ集。でも普通は自分からは言い出さねえよなあ、やっぱ。
ウィズ・ユー 若槻調査事務所の事件ファイル保科昌彦/東京創元社
10/08/21 格納先:は行の作家

若槻調査事務所を訪れた男。娘が誘拐された、身代金受け渡しの場から犯人を尾行し、金と娘を取り返して欲しいという依頼に驚く所員。しかしどうも話が噛み合ない。よくよく聞いてみると、オンラインゲーム“ウィズ・ユー”という仮想空間での出来事だった。個人情報は分からずアバターのルックスは自由に変えられる、そんな空間で果たして誘拐犯を捕まえることはできるのか──?
あたし自身がゲームをやらないので、ここで描写される“ウィズ・ユー”という設定についてのコメントは何もできない。恣意的じゃないかとツッコむだけの知識も、すごくリアルだと感心するだけの知識もないんだもん。バーチャルがリアルってのも変な言い方だけどさ。あたしが知っている最新のゲーム事情がWii Fit Plusだけというせいもあり、“ウィズ・ユー”内に登場するアバターもWiiの似顔絵的なものを想像しながら読んでたくらいだ。どうももっとリアルな映像らしいぞと気付いたのは、物語も中盤になってからだってんだから推して知るべし。
ということで“ウィズ・ユー”絡みのパートについては「ほうほう、そういうルールなのね」ただ素直に受け取るしかできなかったわけだが、現実世界とリンクしてからは俄然前のめりで読み始めた。リアルの方の誘拐事件については、あっと言わされたし。この誘拐事件のくだり、その手法といい背景といい、けっこう練られている。過去の一事件としてあっさり流しちゃもったいない。もっともっと前面に出してドラマチックに演出してくれても良かったのにぃ、と思ったくらい。
これっておそらくはシリーズ物になるんだろうけど、そのせいなのかな、若槻調査事務所の面々についてはしっかり肉付けされていて、個性もあって、生活もあるって感じがはっきり出ていてとても良い。もっと読みたいと思わせる。でも残念なのはその一方で、事件関係者の方が軒並み薄いってこと。特に“ウィズ・ユー”を展開している会社の社長令嬢がなあ……こういう状況ではこう、ああいう状況ではこう、という“フィクションに於ける美女の類型”めいた言動しかとらないってのが気になった。実は、あまりに言動が類型的なので、彼女は実は、過去のハードボイルドに登場する女性キャラクタの言動をインプットされたアバターで、リアル社会の話と見せかけて実は仮想世界の話だったというオチなんじゃないかと本気で推理していたほどだ。後半はキーパーソンになってくるだけに、もっと人となりが浮かび上がるようなリアルな個性を見せて欲しかったな。
水魑の如き沈むもの三津田信三/原書房
10/08/21 格納先:ま行の作家

この「○○の如き●●するもの」シリーズ(なんてそのまんまの命名か)はホントに面白いなあ。元来ホラーが苦手、本格ミステリは大好きだがイカニモ本格の舞台然と拵えられたリアリティの無い設定も苦手、というあたしにとって、まさに鬼門であるようにも思えるシリーズなのに。そんな趣味嗜好にも関わらず本シリーズが面白く感じるのは即ち──ホラーなんだけど怖くない、本格なんだけどイカニモ本格然としていない、ということになる。いや違うな、怖いんだけどそう感じない、イカニモ本格然とした舞台なのにそう感じない、ということだ。あ、これはあくまでも自分基準の印象の話ですからね。
戦後十年経ったか経たないかってあたりの奈良が舞台。民俗学に造形の深い作家の刀城言耶は編集者の偲とともに、古くから変わった雨乞いの習慣を持つという村へ出向いた。その雨乞いの儀式を見学するためだが、その場で殺人が起きて──という話で、この村に住む少年・正一の生立ちや家族の話を挟みながらの二視点で物語は進む。
儀式の習慣様式ひとつひとつの裏に潜む真実をくみ上げ、別枠で語られた少年の生立ちがそれときれいに融合し、二転三転どころか七転八倒(?)するような推理の道筋を示す。これらがもう、いちいち面白い。知的刺戟に満ちていて、事件なんか起こらなくていいから、その地名や儀式の講釈をもうちょっと聞かせちゃくれないかね?という気分になる。そしてそういった民族学的情報の数々が、単なる蘊蓄ではなく、ちゃんとミステリとして生きて来るからすごいのよ。
ホラーなのに恐ろしくはないのも、そしてイカニモ本格ミステリっぽい舞台なのにも関わらず虚構色が薄いのも、まず探偵役のこの学究的な姿勢のせいだろう。虚仮威しに乗らず、事象をひとつひとつ飄々とその場で(これ大事!)解き明かしてくれる。推理の出し惜しみをしない。そこに偲や、今回は村の青年・游魔のポップな掛け合いが混じるので、恐ろしいより楽しくて、彼らの会話をもっと聞いていたくなるのだ。そして面白がっていると──背負い投げを食らうことになる。
ところで「はじめに」を読むと、本編は著者(刀城)の視点で書かれているが、正一の話は分量が多かったため、分けて正一視点の三人称で記述したと記されている。そして「正一氏と同じ手法で描いた人物が、もうひとりだけ存在するが、こちらは彼よりも生の姿を記せたのではないかと自負している」とある。これは単行本458ページから始まる章のことだろうが……そうか、考えてみればこの章も「刀城言耶」が書いてるんだ! うわははは、そう考えるとめっちゃ笑えるぞ。しかも「生の姿を記せた」って……なんて人の悪い!
いや、待てよ? 当然編集者チェックは入ってるわけで……となると生の姿ってもしかしたら……などと考えるのもまた楽しい。うん、やっぱぜんぜん怖くないや。
